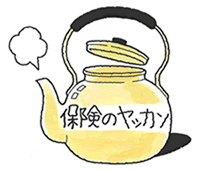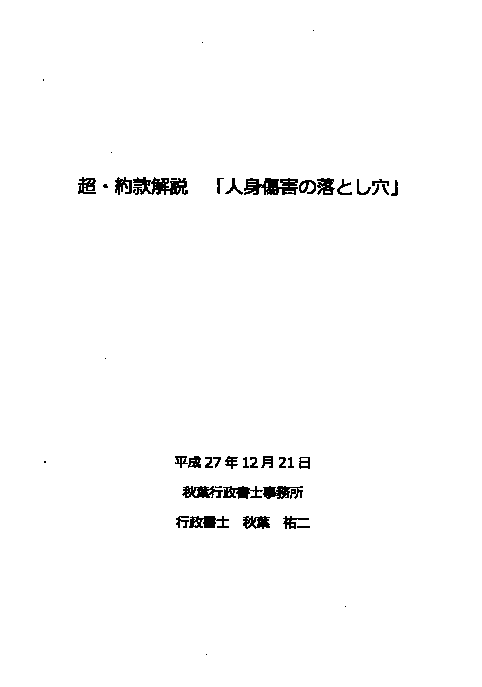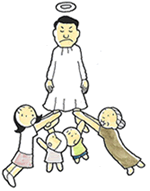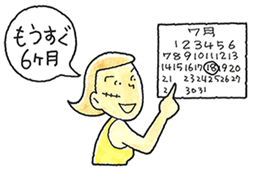前回まで3メガ損保の約款を精査しました。その他の会社に目を移しましょう。
あいおいニッセイ同和さんは損保J日興に同じく、「人身傷害は裁判基準」と潔くなっています。また、同じく掛金の安い、人身傷害が付いていない保険の場合は無保険車傷害特約の適用になります。その無保険車傷害の支払基準は三井住友のように、「当社との協議、それでまとまらなければ当社と裁判か調停をして下さい」ときました。加害者と裁判して、地裁で審議が終わっているのに、再び人身傷害の請求で裁判させる気でしょうか?なんたる不毛感、契約者を愚弄していると言っても言い過ぎではないような気がします。
この、あいおいニッセイ同和型も1つのパターンとしましょう。これは「人身傷害は裁判基準、無保険車は原則・人傷基準&自社との交渉・裁判」型と呼ぶしかありません。そもそも数年前は全社、無保険車傷害は相手との裁判での判決額、つまり、裁判基準を認めていたのです。
このように会社ごとに約款改定が進み、細部が違っています。面倒ですが、それぞれの会社の約款も確認しなければなりません。小さいに字に眼がしょぼしょぼ、おかげで老眼が進みます。
まずは人身傷害、5年前のアンケート結果を確認します。平成23年6月、北海道の消費者団体がこの問題について、「訴訟基準差額説」or「人傷基準差額説」のどちらで支払うのか損保各社に質問状を送りました。回答は以下の通りです。
今日の内容がわからない方⇒訴訟基準差額説、人傷基準差額説
会社名
賠償義務者への 訴訟が先行した場合
人身傷害保険の 支払が先行した場合
改訂時期
回答
回答
あいニッセ同和H22.10.1
訴訟基準
訴訟基準
アクサH22.4.1
人傷基準
訴訟基準
イーデザインH23.4.1
その他
訴訟基準
共栄火災H23.4.1
その他
その他
セコムH23.4.1