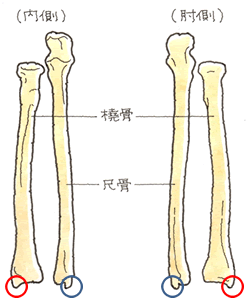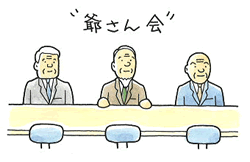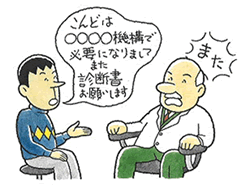毎度、セミナーでは色々なご質問を頂きます。それらに回答をすることで、セミナーをする側も大変に勉強になっています。勉強会を重ねることに、私達も鍛えられているのです。 前回の質疑応答を1つご紹介しましょう。(守秘義務に則り、内容を改変しています) Q1) 物損事故で、当方・相手の保険会社同士で話し合いが進められています。ところが、相手側が交渉内容に納得せず、自分の保険を使わないと言い出しているそうです。相手保険会社の担当者も、「契約者が保険を使わないと言っている以上、当方は何もできません」と言っています。私は保険会社同士の話し合いに任せたいと思っています。どうしたら良いでしょうか? A1) 相手はグズリ得を狙っているのでしょうか。また、相手保険会社の担当者の言う「契約者が保険を使わない=保険会社は何もできません」は一見、納得しそうな話ですが、納得してはいけません。そんな、理不尽は許せませんし、相手保険会社に引っ込まれては困ります。したがって、相手の任意保険の「直接請求権」を発動させます。これは、被害者が、相手契約者抜きに、相手の保険会社に直接賠償請求できる約款条項です。しかし、この直接請求権には発動条件があり、一部には相手の意向も絡むので、少しコツがいります。以下の条件をもって、相手保険会社を再度、引きずり出すことができます。 ① 保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
④の相手の死亡は別として、②~③のように、相手の同意ありきなので、すったんもんだしている間に、結局、相手が折れて通常通り保険使用となることもあります。また、相手のグズリに屈して自損自弁(お互い自分の車は自分で修理)となることも多いようです。つまり、実際にはこの条項が発動されることは稀です。そのせいか、信じられないことに、この保険約款の存在すら知らない保険担当者がおります。多くはすっとぼけているのではなく、本当に知らないのです。
直接請求権を理解するには、実例での解説が必要です。以下のストーリーを熟読して、解決までのロードマップを敷いて下さい。
⇒事故の相手が保険を使ってくれない①~⑥
続きを読む »


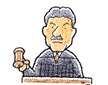
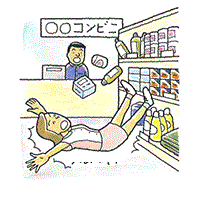 他にもありますが、代表的なものは以上です。
本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。
他にもありますが、代表的なものは以上です。
本件は宿泊施設が加入していた施設賠償保険に頼ることになりました。賠償保険の多くは、自動車の任意保険のように積極的に示談代行ができない上、担当者は自賠責保険の基準で押し切ろうとします。それでダメなら、弁護士介入がパターンです。それでも、保険の加入はありがたいものです。連携弁護士とのコンビでしっかり解決させます。 賠償保険なら何でも来い!
賠償保険なら何でも来い!
 歩行者の責任も問うべきと思います
歩行者の責任も問うべきと思います
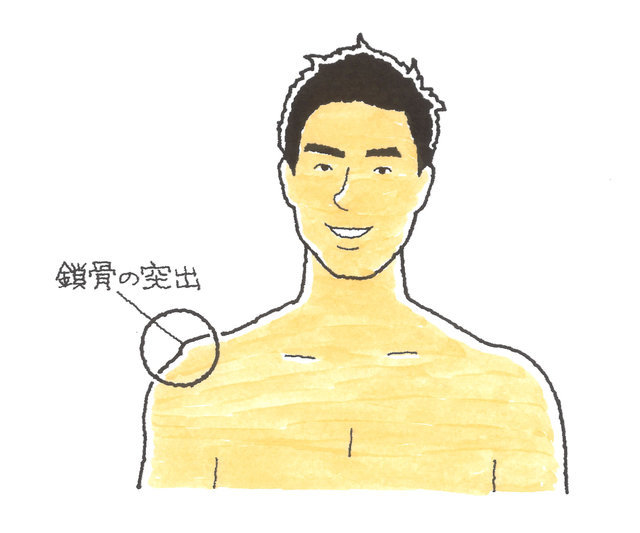
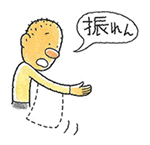 自転車対歩行者、あるいは自転車同士の事故は交通事故相談の中でも、実はかなりの数なのです。私達が注目することは、やはり、個人賠償責任保険です。相手に保険があること、すなわち、回収の問題をクリアできるのです。加害者のお財布から治療費や慰謝料を取ることは非常に難しく、相手に資力がなければ「ない袖は振れん」と・・お手上げです。どんな敏腕弁護士でも苦戦必至、あるいはあきらめとなります。
自転車対歩行者、あるいは自転車同士の事故は交通事故相談の中でも、実はかなりの数なのです。私達が注目することは、やはり、個人賠償責任保険です。相手に保険があること、すなわち、回収の問題をクリアできるのです。加害者のお財布から治療費や慰謝料を取ることは非常に難しく、相手に資力がなければ「ない袖は振れん」と・・お手上げです。どんな敏腕弁護士でも苦戦必至、あるいはあきらめとなります。 日々、保険の勉強が大事です
日々、保険の勉強が大事です