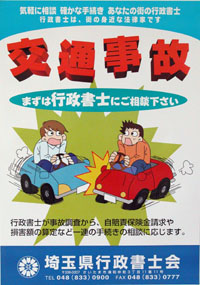昨日までの話・・
1、行政書士も交通事故を業務とするものがいます。まだ認知度は低いと言えます。
2、交通事故のほとんどが 保険会社vs被害者 の構図となっています。しかし被害者は苦戦必至です。
● では、被害者に代わって保険会社と対するは・・・もちろん弁護士です
「いざとなったらやはり弁護士」、この認識は十分に行きわたっています。しかし同じ弁護士でも「交通事故業務が実務上できる弁護士」と「資格があるから法律上可能な弁護士」に2分すると思います。そして前者はかなり少数です。
興味深いデータがあります・・・ 昭和48年に7000件を超えた交通事故損害賠償請求訴訟ですが、昭和49年3月に示談交渉つき保険が発売されるや、翌年には訴訟件数が1000件を切りました。以後示談は保険会社vs被害者本人 の構図が主流となったのです。
つまり保険会社は、抜群の商品開発力で様々な保障・特約を作り上げ、弁護士から交通事故の経験則を奪い取りました。 近年、訴訟件数も5000件超に回復していますが、全国の弁護士の数からすると、めったに交通事故訴訟は扱わない?といった結果になります。もちろんほんの小数である交通事故業務に特化した事務所がこの多くを受任していますので、ほとんどの弁護士は交通事故訴訟の経験が得られない状況です。交通事故に不慣れな個人事務所が知人から交通事故裁判を持ちかけられも、本来は断るべきなのです。
実例を挙げます。
<実例1> 和解するくらいなら・・・
被害者Aさんは交差点で車同士で衝突、大ケガを負いました。脛骨、腓骨(すね)の骨折です。後遺障害は11級が認められました。 しかし自分にも過失があり、相手の保険会社が提示する賠償額は30%減額されたものです。
提示額は・・・既払い額を除いた損害額は約1000万円、過失割合は 自分30:相手70 なので受取額は1000万円×70%で700万円です。
Aさんは悔しくて訴訟をしようと弁護士を探しました。そして知人の紹介でB弁護士に依頼しました。その弁護士は交通事故を年2~3回扱っているようです。
B弁護士は受任し、過失割合について裁判で20:80の主張を展開しました。請求額は約3000万です。
相手保険会社も顧問弁護士をたてて、類似判例をドーンとだしてきて過失割合の正当性はもちろん、顧問医の意見書で医療上の見解を展開、さらにAさんの収入面について厳しく指摘が続きます。対するB弁護士も昨夜一生懸命勉強した資料を提出して応戦します。
そして裁判所から慰謝料を少し上乗せした和解案が提示されました。それからB弁護士は何故かAさんに「私の尽力で賠償額を2倍にしました!これ以上争っても時間がかかるので和解しましょう」と説得を始めました。Aさんも自分の弁護士が言うのだからその方がいいのだろうと和解に応じました。
結果、和解の賠償額は2000万円、過失割合は変わらず2000万円 × 70% で Aさんの受取額は1400万円です。 しかしここから弁護士報酬が支払われます。すでに着手金で100万円を支払い、報酬で140万円です。
元々保険会社の提示で示談だったら700万円です。裁判で1400万円になりましたが、弁護士費用を差し引くと1160万円です。なんか釈然としないAさんですが、一応460万円増えたので良かった結果になります。
しかしこの業務は問題山盛りです。① 過失割合は30:70から変わらないので、争点から言ったら負けです。徹底的に争う気がないのなら最初から20:80は困難と説明すべきです。最初から和解ありきで20:80の気鋭を上げただけ?のように感じてしまいます。
② これは後遺障害11級のケースです。過失割合を徹底的に争わないのなら、交通事故紛争センターの利用も考慮すべきです。和解で用いられた基準同様の赤本基準でざっと計算するとやはり損害額は2000万円位なり、紛争センターの斡旋案が仮に赤本の8割程度の1600万円で、ここから過失分30%を引かれても1120万円になります。そうです、和解案と大差ないのです。紛争センターの無料斡旋弁護士の方が、よりいい数字を引きだす可能性すら感じます。③ 脛骨・腓骨の骨折で11級が妥当だったのでしょうか?後でわかったのですが、この方は完治後も足首と足指の曲がりが悪く、リハビリしても改善しません。軽度ですが腓骨神経麻痺の可能性大です。この場合足首10級、足指12級で併合9級の芽がありました。 過失割合ばかりに目が行って、争点を間違えています。11級→9級となると受取額は1000万円程増えます。過失分10%の200万円程度を争っている場合ではないのです。医療立証を行い、異議申立→裁判、という道筋を取るべきだったのです。
④ あと、最低これだけは説明すべきです。判決まで争った場合、相手から弁護士費用、賠償額の10%程度が認められます。(最近は和解でも若干認定されるようになりました)。さらに事故日からの遅延利息金、賠償額の年利5%(この低金利の世の中で!)が加算されます。Aさんにこの説明をした上で和解と決めたのでしょうか?
これは特異な例ではありません。保険代理業20年を通じて経験した交通事故裁判は全件 和解でした。判決まで争う例は極めて少数なのです。このB弁護士も勝ち目がないのを承知で、報酬の為に和解前提で受任したのでは?と疑ってしまいます。そして当然ながら百戦錬磨の保険会社の担当者や顧問弁護士、顧問医と戦えるだけの経験則を持っていません。
続きを読む »