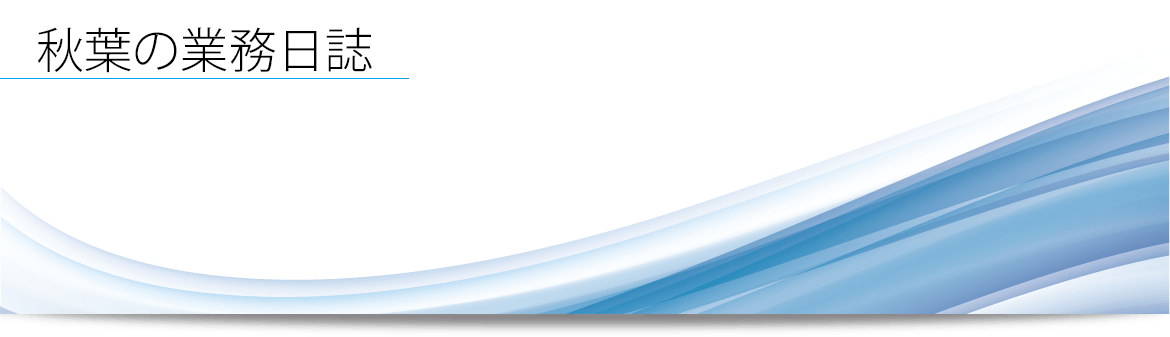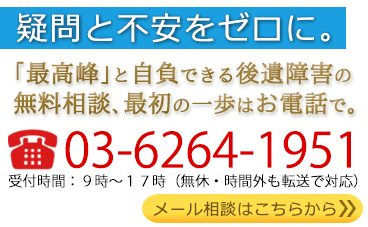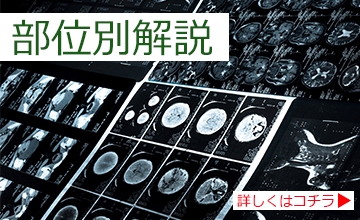今年の『損害賠償算定基準2018・下巻』(いわゆる赤本)引用、 武富 一晃 裁判官 の解説を続けます。
(2)以下、どのような場合にどの計算方法を用いるべきか、給与所得者が継続して完全休業する場合と給与所得者が就労しながら一定の頻度で通院を行っている場合に分けて検討していきます。
2 給与所得者が継続して完全休業する場合
休業損害は、事故による受傷を原因とする休業のために支給を受けられなかった減収分(差額)について認められるところ、労働契約上、勤務時間等が定まっていて、実際に労働した時間に応じた金額の給与が支給されている給与所得者については、休業損害を正確に算定するため、計算方法 ②で収入日額を算定し、これに実際の休業日数を乗じる方法((b)の計算方法)によるべきという考え方もあり得ます。
しかし、完全休業の期間がある程度長期の場合には、(a)、(b)の計算方法のいずれを採用しても、結論に大きな差は出ません。また、休業損害は、事故後も事故前と同様に勤務を続けたという仮定的な状況において得られたはずの給与と現実に得た給与の差額を算定するものであること、給与は、基本給のほか、時間外・休日・深夜労働の割増賃金や歩合給を含む諸手当の金額、時間外労働や休日労働を含む実際の労働時間によって決まるものであって、同じ労働契約のもとでも、金額が期間ごとに変動することから、その性質上、厳密な意味で正確な休業損害を算定することはできません。
したがって、ある程度長い期間継続して完全休業する場合には、(a)(b)の計算方法のいずれかを採用してもよいと考えられます。実務上、(a)の計算方法が採用されることが少なくないのは、このような事情によるものと思われます。

長期休暇となると、休業損害より会社の休業規定が気になります。
3 給与所得者が就労しながら一定の頻度で通院を行っている場合
(1)給与所得者には、一般の会社員や公務員のように、労働契約上、就労日、労働時間が定められており、実際の労働時間に応じた金額の給与が支払われる者が多いと思われます。これらの給与所得者については、適切な証拠があれば、事故前に支給された給与の金額に基づいて実労働日1日当たりの平均給与額を算定することができますし、労働契約上、就労すべき日が定められていることから、通院等をした日のうちのどの日が、交通事故がなければ就労していたはずの日であるかを認定することができます。したがって、被害者側が(b)の計算方法によるのが相当ということができます。このような場合に、(c)の計算方法を採用すると、収入日額が低くなり、理論上は休業損害を過少に認定することとなります。
しかし、実務上、被害者側が(c)の計算方法で算定した休業損害を請求する事案は少なからずあります。たとえば、休業損害証明書が提出されないなどの事情で、証拠上、事故前の一定期間の実労働日数とその期間に対応した給与支給額を認定することができない場合には、(c)の計算方法(たとえば、事故前年の源泉徴収票記載の給与額を365日で割った金額を基礎収入とし、これに実際の休業日数を乗じる方法)によって休業損害を算定せざる得ないことがありあす。
また、休業損害を請求する被害者の立場からは、上記のような立証の問題のほか、収入日額は諸手当の金額や実際の労働時間等によって金額が変動し、正確な収入日額を算定することが必ずしも容易ではないことをふまえ、より確実に発生したといえる範囲で休業損害を請求することもあると思われます。このように、当事者の主張の内容や証拠関係によっては、(c)の計算方法をとることが適切といえる場合もあるといえます。
 農業・漁業などはシーズンによって収入の増減が激しく、勤務日・休日の区分けも困難になります
農業・漁業などはシーズンによって収入の増減が激しく、勤務日・休日の区分けも困難になります

自由業、複数の兼業、これらの計算も証拠が弱くなります
自営業者の源泉徴収票も”勤務時間に対応する収入”が計算しづらく、それを明らかにする別紙(勤務表と賃金台帳など)で立証できないと、(C)方式の余地を残すことになります。
つづく